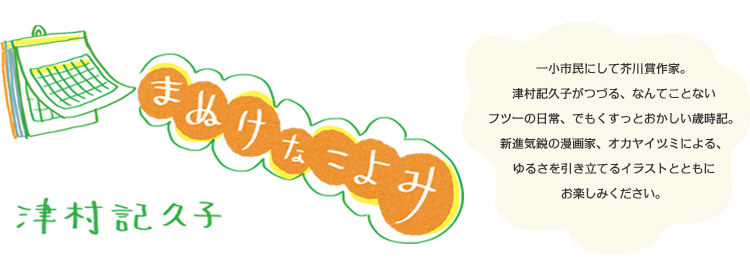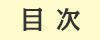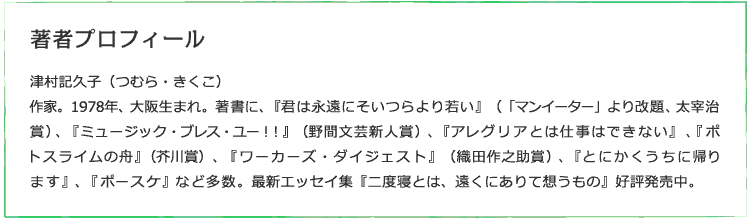2月20日はアレルギーの日だという。免疫学者の石松公成・照子夫妻が、アレルギーを起こす原因となる免疫グロブリン(IgE)抗体を発見し、アメリカの学会で発表した日を記念してということだそうだ。
アレルギーとはそもそも何か? 手元の新明解国語辞典によると、「注射や、特定の飲食物・薬を摂取した場合に、体質上、正常者とは異なる過敏な反応を示すこと。(略)〔広義では、特定の人・物事に対する拒絶反応を指す〕」とある。この時期にアレルギーというと、それはもう花粉症の出番ですね、という感じなのだが、いまだ花粉症デビューは免れているわたしも、アレルギー体質ではあるようだ。小児喘息だったし、春先になると、2年に1回ぐらいの割合で長く咳が出ることがある。
それまで数年の間は、あまりひどい咳に見舞われることはなかったのだが、去年はけっこうひどいのにやられた。まあ風邪だろ、と思い込んで、いっこうに治らないなあ、とのんびりしていたら、咳はどんどんひどくなっていった。3月の始めごろから4月の中旬までは、ずっと咳をしていたように思う。けっこう派手に咳が出たので、いろいろな人に心配をかけた。
何が申し訳ないって、わたしは小児喘息を患っていたので、本人は変に咳をし慣れているというのに、周りの人が気遣ってくれることだった。げほげほしながら、どこかで咳を咳とも思っていないようなところがあるのだ。特に、空咳との組み合い方には、自分の中で密かに定評があるように思う。げほげほならまだいい。いちばん重い時は、ブォ、ブォッという感じの、バイクのエンジンをふかすような咳が出る。あれが出ると、本領発揮って感じだな、とわたしはニヒルに思う。咳はわたしのスパーリングパートナーであるとも言える。何の。
とにかく自分はアレルギーによる小児喘息であるという自覚は、幼稚園の年少さんの頃からあり、それが幼稚園児なりの数少ないアイデンティティの一つだったので、家族旅行で白浜に行くたびに(南紀白浜が好きな一家だったのである)、「白浜エネルギーランド」を「白浜アレルギーランド」と言い換えるというギャグまで飛ばしていた。書いていて、わたしならこんなやつ心配しない、と思う。この文章が公開されて、どうせ津村さんは咳慣れしてるんでしょ、アレルギーランドなんでしょ、ということが周囲にばれてしまうのは少し怖い。今は幼稚園の頃ほどは咳をするのが日常ではないので、それなりにダメージは受けています。あしからずです。
ここまで言っておいてなんだけれども、咳はとても嫌なものだと思う。ただ、ものすごく身体性があるものでもある。1回の咳で、50メートルだか100メートルだかを走るのと同じぐらいの体力を消費するのだとまことしやかに言われているように、咳をするという体の内部から外部への動きは、驚くほどの注意を伴う。自分はあまりにも体の中にいる、といやがうえにも思い知るのである。発熱には、体力を空気の中に蒸発させていってしまうような苦しみがあるけれども、咳は、自分の魂のようなものの破片が排出されていくような感覚がある。強烈な動作をしているという感覚である。そういうことを経験すると、ほとんど自分に体があるということを意識しないような、風景の中に溶け込んでいるような自失に近い瞬間こそ、これが十全なのではないかと思えてくるのである。たとえば、駅でひたすら電車を待っているような、ほとんど身体性のない時間に、もっとも中庸な生きている感覚はあるのではないかと。「する」のではなく「しない」ことの中に。
去年私がおこなった咳への対策は「する」ことの連続だった。咳止めパッチというものをもらって、腕にびっと貼ってうれしがる、咳止めシロップを服用し、気管拡張の薬を飲む。咳止めシロップは子供のころ好きだったので、ちょっとよろこんで飲んでいた。四月の中ごろになると、咳は自然とやみ、わたしは元の特に問題のない倦怠の中に戻っていった。べつに咳がいいとか懐かしい、というのではないけれども、「あれ? 咳が出なくなったよ?」という瞬間の拍子抜けというか、おっという感じは、けっこう得難いものがある。もし今年咳が始まっても、あの感じを楽しみに暮らしたいと思う。