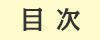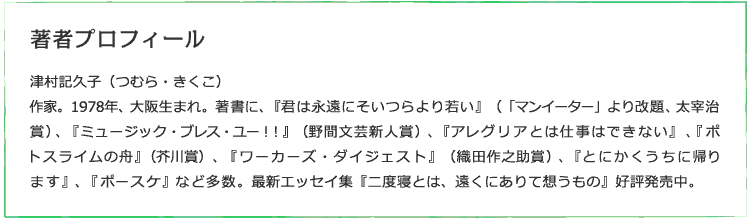ぶらんこがすごく好きな子供だった、というか、だいぶいい年になった今も、隙あらば乗りたいと思っている。子供の頃の趣味は、読書と自転車に乗ることとぶらんこだった、といっても過言ではない。
ぶらんこはとても楽しい。座って思い切り後ろから人に押してもらうのが好きなのだが、立ちこぎで限界までこぎまくったのち、おごそかに座って、ぶらんこに乗っていないときには見ることができない別の世界を見るのも劣らず楽しかった。遠心力の手に体を預けつつ、目まぐるしく風景が遠くなったり近くなったりするのを凝視しながら、自分の体が空気をかき回すというあの体験は、大人ならばエクストリームスポーツぐらいでしか体験できない強烈なものなのではないか。子供はそれを、ぶらんこでお気軽に毎日でも楽しめる。ぜいたくだったな子供の頃は。
小学1年の2学期から、3年の1学期まで住んでいた団地には、ある会社の社宅が隣接していて、どちらにも公園があり、ぶらんこもあったのだが、わたしは自分が住んでいる団地の方ではなくて、社宅の方のぶらんこが好きだった。今考えると、社宅に住む人たちは苦々しく思っていたのではないかと不安になるのだが、子供には団地の公園も社宅の公園も同じ公園なので、テリトリーの意識はなく遊んでいた。
社宅の公園のぶらんこの方が好きだったのは、団地のぶらんこより大きかったからだと思う。ただ、大きなぶらんこにはトレードオフの要素があって、近くに桜の木がたくさん植わっていたのである。え、桜があるならきれいだしいいじゃないかって? いやいや。その社宅の桜の木々には、毛虫がついていたのだった。わたしは直接毛虫の害を被ったことはないのだが、たとえば、すべりだいをすべっていて毛虫をしりでつぶしてしまうとか、ぶらんこをこいでいるときに腕に毛虫が落ちてくるだとかいった想像は、わたしを含めたぶらんこで遊ぶ小学生たちには、恐怖でしかなかった。大人になった今でも、書いていてちょっとぞっとするものがある。
なので、その社宅のぶらんこには、子供が集まる繁忙期と、誰一人寄りつかない閑散期があった。桜の木に毛虫がいる夏は言うまでもなく閑散期で、秋になるとおそるおそる子供たちが周囲に戻り始め、でも冬はあまりにもぶらんこの鉄の鎖が冷えてこぐ気にもならず、そして春は取り合いである。
余談だが、実は小学2年の頃、その社宅の桜が風に散って、地面の上で渦を巻いている様子をテーマに、きわめてセンチメンタルな詩を書いたことがあるのだが、わたしの書いた文章を母親がほめてくれたのは、人生であれが最後のような気がする。
わたしの小学校低学年期における記憶の2割ぐらいは、ぶらんこ関係のことだと思う。ぶらんこが楽しかった。何々ちゃんはぶらんこをよく押してくれてとてもありがたい人だった。ぶらんこから落ちて膝を擦り剥いた。ぶらんこから落ちて真下に埋まっていた石で頭を打った。ぶらんこの近くで遊んでいてぶらんこ自体で頭を打った。特に、ぶらんこの真下の石で頭を打ったのは異常に痛かったので、今もその石がどんな石だったかを覚えている。真っ黒でなめらかな大きな石だった。どうしてそんな石があったのだろう。何か、調子に乗りすぎるなよ、という戒めを想起させる、威厳のある石だった。よくそれだけ頭を打っていて死ななかったなとも思う。体験のエクストリーム性も併せて、よく考えたら、相当ハードな遊具なのではないか。
いや、にこにこ笑いながら、穏やかにぶらぶらこぐなど、ソフトな遊び方もできたのかもしれないが、わたしにとっては、ぶらんこをリラックスしてこぐなんて、時間の無駄でしかなかった。ぶらんこに乗ったからには、いつも本気だった。ぶらんこは、そのポテンシャルを最大に引き出さんばかりに必死で接したならば、自分の感覚を非日常の域まで拡大してくれる、魔法の遊具だった。だからこそわたしは、あんなに頭を打っても、膝を使いまくってぶらんこに乗り続けたのだと思う。
ぶらんこで一回転することが夢だったが、実現しないまま大人になってしまった。そのことを今も悔やんでいる。そして桜が散る時期になると、自分がなぜか詩を書いたことと、それに引きずられるように、あの社宅のぶらんこと、その下に埋まっていたなめらかな黒い石のことを思い出すのだ。