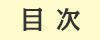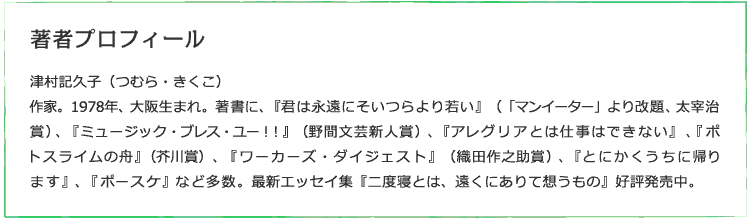5月5日は、こどもの日であると同時に、自転車の日でもあるらしい。子供と自転車は親和性が高いので、まったく違和感なく、自転車に乗っている子供のことが頭に浮かぶ。たまに怖いんだけれども、自転車に乗っている子供。なんというか、自分の脚で苦もなく自由に速く走れる、ということに、あまりにも興奮して身体を預けすぎていて、びっくりするほどスピードを出し、危ない運転に興じている子がよくいる。でも、腹が立たないというか、ただ仕方ないなあ、という気分になる。自分も自転車を与えられたときの万能感をよく覚えているので、自分の脚で徹底的にスピードに乗っていきたい気持ちは理解できる(ただし、自転車でスマホを使いながら、我が物顔で道を蛇行しているような大人は本当にみっともないです)。
自転車については、どこから話し始めたらいいかわからない。わたしは毎日のように自転車に乗っていて、テレビでもサイクルロードレースの番組を見るのをとても楽しみにしている。子供の頃も学生の頃も、会社に行き始めてからも、そして今も、自転車は生活に欠かせない。2年前に、それまで乗っていたママチャリを無断駐輪していたために撤去されてから、近所にはできるだけ徒歩で出かけたり、散歩にもよく行くようになったのだが、歩くことによる気持ちの浄化の作用に気づくにつれ、不思議なことにますます自転車への思い入れも高まっている。運動が好きとはとてもいえない人間だけれど、脚を使って動くことはかなり好きなのだと思う。徒歩には徒歩の、自転車には自転車の良さがあるのだが、気持ちがふさぎ込んで苦しいときは、なんといっても自転車に限る。普段使いのママチャリを失って、ガレージに入れたままにして大事にしていたクロスバイクに乗り換えたことによって、自転車に乗ることの質が上がったのかもしれない。
幼稚園の年長さんのあたりから乗っているので、もう三十数年自転車にはお世話になっていることになる。それぞれの年代の自転車の乗り方があったと思うのだけれど、高校が自転車通学であったことが大きかったように思う。他の生徒が電車に乗って学校に来ることによって、大人への階段を上るためのある種の社会性を身に付けていったのに対して、わたしはただただ毎日ものすごい速さで、駅から校門に向かう彼らを追い抜かして自転車で走っていた。今でもそのことは友人の話題にされる。風のようだったらしい。放課後は自転車に乗って難波や心斎橋や通天閣や電気屋筋(日本橋のこと)に遊びに行った。今考えると、非常に充実した自転車通学生活であったと言える。そうやって自転車通学には長けていったものの、電車の乗り方はほとんどわからなかったので、いきなり京都の大学に行くことになったときには往生した、ということは前々回の通りである。
当時はもう、身体の動くままに元気に自転車に乗って楽しんでいたのだが、今は元気が出ないときこそ自転車に乗るようにしている。自分の部屋で、どうにも気分がふさぎ込むと、とりあえず自転車に乗ればましになる、とばかりに出かけてゆく。自分の部屋には何の解決もなくて、自転車にはそれがある、という頭の中の取り決めがつくづく不思議に思える。自転車はそんなに万能なものではないし、自転車に乗ることもまた現実なのに、わたしは何かというと仕事をリュックに詰め込んで、自転車に乗って、ちょっと遠くまで走っていく。出先で作業をこなして、またびゅんびゅん走って帰ってくると、出口のない気分は少し何とかなっている。単に作業を片づけたせいもあるのだろうけれども、作業をしようという気持ちになれるのも、往路で自転車に乗ったからだろう。
ディセンデンツに「Bikeage」という有名な曲がある。自分の『ミュージック・ブレス・ユー!!』という小説の冒頭でも引用した。このタイトルは「自転車の頃」と訳したらいいのか。知り合いの女の子が麻薬中毒になって身体を売ったりしているのを、語り手の少年が「おれは君を使わない」となすすべもなく見つめながら、でも君が必要なんだと想っているというような内容の曲である。重くシビアな歌詞にもかかわらず、曲はとても軽快で明るい。語り手の年齢はわからないけれども、女の子は15歳で、曲が収録されているアルバム「Milo Goes To College」は、曲を作ったビル・スティーヴンソンが19歳のときにリリースされた。だから、「Bikeage」とは、おそらくそのへんの年齢のことを指すのだと思う。わたしがディセンデンツをよく聴くようになったのは、20代も後半の頃からだったが、この無力感と痛切さは本当によく理解できる。手に取るようにわかると言ってもいい。そんなものはわたしの主観にすぎないとしても。
ままならない現実を乗せて、時と澱を振り払いながら走る。自分にとって自転車に乗るということは「Bikeage」という曲そのものの在り方にとても似ている。自転車に乗ると、自分が何者であるかを忘れて、何者でもなかった頃に戻るような気がしてくる。そこには、自分の部屋が溜め込んだ複雑さから逃亡して、身一つで空気の中に投げ出されることの、ほとんどやけといっていい爽快さがある。だからどうしても、自転車ですっ飛ばす子供たちにえらそうに「やめろ」とは言えないのだった。