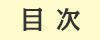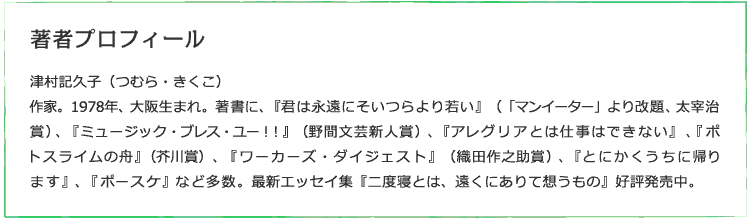今回のテーマは「カビ」ということで文章を書くのですが、ひとまず聞いてください。わたしは先日食中毒になりました。おにぎりを夜中に作って常温で置いておいたものを、次の日の夕方に食べたのですが、その1時間後に激しい嘔吐を繰り返しました。生まれて初めて、道で吐きました(側溝なのでどうか許してください)。道路のこっち側と向こう側で、1回ずつ吐くという珍しい経験をしました。出先と自宅であわせて20回ぐらい吐きました。3時間ぐらい大変な思いをしたのち、あっさり症状は引き、心が弱っていたのか、夜に放送されていたジロ・デ・イタリアの山岳ステージをぼーっと観ながら、なぜか涙が止まりませんでした。12月にこの連載(第五十三回)でとりあげた、イゴール・アントンのいたチームである元エウスカルテル・エウスカディの選手が活躍していたからかもしれませんし、久しぶりにアントン自身をテレビで確認したからかもしれません。ものすごく、わけのわからない日でした。みなさん、時間のたった手作りのおにぎりには気を付けてください。
おにぎりを常温でそんなに長い時間放置するなという話なのはわかっているけれども、冬場は大丈夫だったのだ。それで久しぶりに余裕ができて作ったらそのざまなのである。「梅雨やからなあ」とこの話を聞いた友人は言っていた。そういうわけで、刻一刻と夏に向かって油断のならない日々が続いている。夏め。冬に向かう油断のならなさって、ただ寒くなるだけだろう。それに比べて夏は食べ物まで腐らせやがる。ひどい話である。
わたしはきわめてがさつな暮らしをしているので、カビとそんなに親和性がないわけではないと思う。がさつな上にパンが好きなので、よく買い込んではすぐにカビを生やすし、今の家に引っ越してきて、フローリングに直接布団を敷くとカビが生えるということを知った。それまでは知らなかったので、しばらくカビの生えた布団の上に寝ていたわけなのだが、特にどうということはなかった。なので自分はカビ慣れしている方だと考えていた、言うなれば。ゆえに、その親戚のようなものである菌にあそこまでやられるということがショックだったのだ。えー、わたしはあなたたちにあんなに鷹揚(おうよう)に接してきたじゃない、というすごく勝手な感情なのだが、ちょっと裏切られたような気がした。
カビに対してそんなに激しい憎悪を持てないのは、カビには「見える」というわかりやすい特徴があるからかもしれない、と思う。先日のおにぎりに宿った菌は(調べてみるとセレウスという名前のようだ)、まったく見えずに不意打ちのようにわたしを打ちのめしたのだが、カビは見える。まあ、不快な様子ではあるのだが、「おい、生えたぞ気を付けろよ」と見えることによってぶっきらぼうに注意喚起をしている、と考えられなくもない。そうすると、仕方ないな、と思えるのである。あのいただきもののおまんじゅうも、無添加のジャムも、とてももったいなかったけれども、自分の管理の甘さがカビを呼んじゃったからな、仕方ないな、この勝負はカビの勝ちだ、とすみやかに容器ごとごみ箱に捨てる。カビは見えることによって、人間に対してそこそこ節度のある戦いを挑んでいるように思える。そんな勝負はしないに越したことはないのだが、カビはときどき、その姿をあらわすことによってわたしに反省を促す。パンは食いきれなければ冷凍しろ、なまものはもらい次第食え、高いジャムほどさっさと消費しろ、また生えてやったぞ、今度も勝負に勝ったな。カビは、わたしが粗末に取り扱ってしまったものの中ほどに、寡黙に鎮座する。増えたカビが「集落」と称されるのも、どこか意思的だ。隙を見せたわたしが悪いのだ。
子供の頃、食パンに生えたカビを初めて見た時のことを鮮明に覚えている。パンの真ん中に、青くて小さくて丸い、どうもフサフサした感じのものがぽつんと存在している。その、ひっついている、のでも、置かれている、のでもない、妙に自然な侵蝕の様子に感じ入ったものだった。パンは食べられなくなったが、カビは当時のわたしにとって珍しいものだった。臭いもなく、極度にグロテスクでもないそのカビはどこか、粛々としていた。わたしはカビを眺めていたかったが、母親がすぐにパンを捨ててしまったため、どうもいつまでも記憶に残っている。