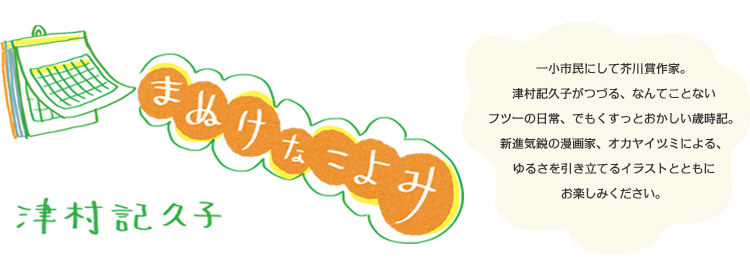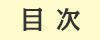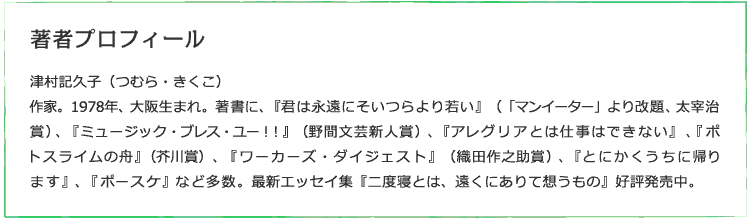刺繍が好きなのだけれども、毎日刺しまくっていると、図案集などで提案される図案だけでは物足りなくなってきたのか、気がついたら海外の無料のクリップアートをアホみたいに漁っていたり、しまいには自分で描けやしないかと模索したりし始めていた。絵心がないにもかかわらずである。クリップアートに関しては、修道士とか消防士とかガスマスクとか、もう完全にこじれきったものを主に探し、自分で描こうとしていたのは鳥の絵である。鳥は、刺繍のモチーフとしてはとても一般的で、べつに自分で描けるようになる必要はなかったのだが、わたしは鳥が大好きなので、そのうちすぐに図案集の鳥を刺し尽くしてしまうだろう、という危惧があった。ので、刺し尽くさないうちから、鳥の絵の練習を始めるという、不気味な段取りさんぶりを発揮していた。
平凡社から出版されている『日本の野鳥650』を資料に、わたしは夜な夜な(正確には夜中の仕事が終わってから絵の練習をするので、朝な朝な)鳥の絵を描きまくっていた。図案集にはない鳥を、ということで、エトピリカやカケスやアジサシなどを描いていた。こちらもやはり、かなりこじらせてしまっていたように思う。結局、練習した鳥の絵は、その後仕事が忙しくなるというきわめて通常の事態によって、刺すということはないまま放置している。
わたしはそうやって鳥の絵の練習をして、鳥の図案のレパートリーを増やすことによって何を避けようとしていたのだろうか? ツバメを刺す日が来ることをできるだけ遠ざけようとしていたのである。
そうなのだ。わたしはツバメがとても好きだ。鳥そのものが好きで、ならどの鳥と一緒に過ごしたいかというとどうしてもヨウムになってしまうし(話せるし)、何か崇めるような感覚で心に留めているのはワタリアホウドリなのだが、見た目という側面ではツバメが好きだ。尾が尖っていて二股に分かれている、というあまりにも素早そうなフォルムをしていたり、そのわりには喉が赤くてかわいらしかったり、本当にすてきな見た目をした鳥だと思う。
そういうわけなので、ツバメは刺繍のモチーフとしてもときどき登場する。わたしはその図案と出来上がりのページを見比べながら、この鋭い尾っぽはサテンステッチではなくアウトラインステッチで刺すのかあ、できるかなあ、くーっ、などと独り言を言う。それが自分に不可能だと激しく思っているなどというわけではないのだけれども、どうしてもツバメの図案は、もっとひどく落ち込んだときに刺したいと決めている。
というか、刺繍の図案までもプールするか、と思う。だいたいわたしは、「この『フレンチ・コネクション』のコメンタリーはもっと大変なときに見よう......」などとそういう保留コンテンツを持ちすぎである。そうやって、DVD、音源、本などをたくさん、消費しないまま手元に置いてきたのだが、刺繍の図案までもか。
好きすぎるために遠巻きになってしまっているツバメだが、さらに悲しいことに、この季節には越冬のため、南へと去っていくらしい。そういえば、半年前に買った陶器のツバメのブローチは、付け始めて1ヶ月もしないうちに、尾の部分が欠けてしまった。その後ボンドで補修はしたものの、ショックは大きい。実はツバメの巣を見たことも、奈良の民家の軒先で一度あるだけだ。わたしは、ツバメが好きなわりにあまり縁がない人間なのかもしれない。
なので、ツバメが南に去る今こそ、ツバメを刺すときなのではないか、という気がしてきた。縁がないのなら無理矢理作るのである。ツバメが迷惑がっても作る。刺しまくるぞツバメ。でも問題が一つある。刺しまくれるほど、ツバメの図案というのはないのだ。だからまた『日本の野鳥650』の出番だ......。刺繍をするためにまずは絵の練習から始める。ツバメへの道のりは相変わらずなんだか遠い。
※「まぬけなこよみ」は今回で最終回です。長らくのご愛読、ありがとうございました。
単行本は来年発売予定、ご期待ください。